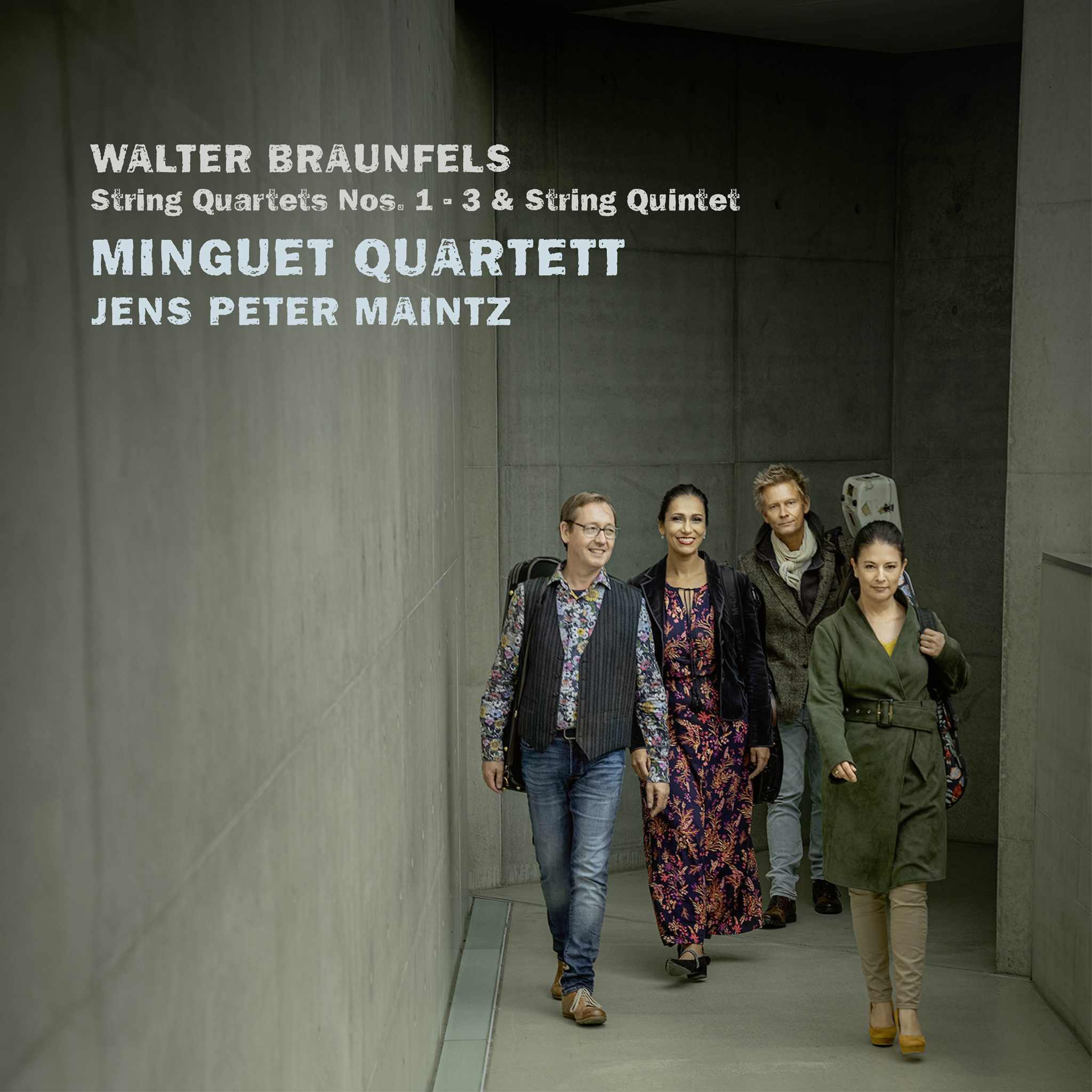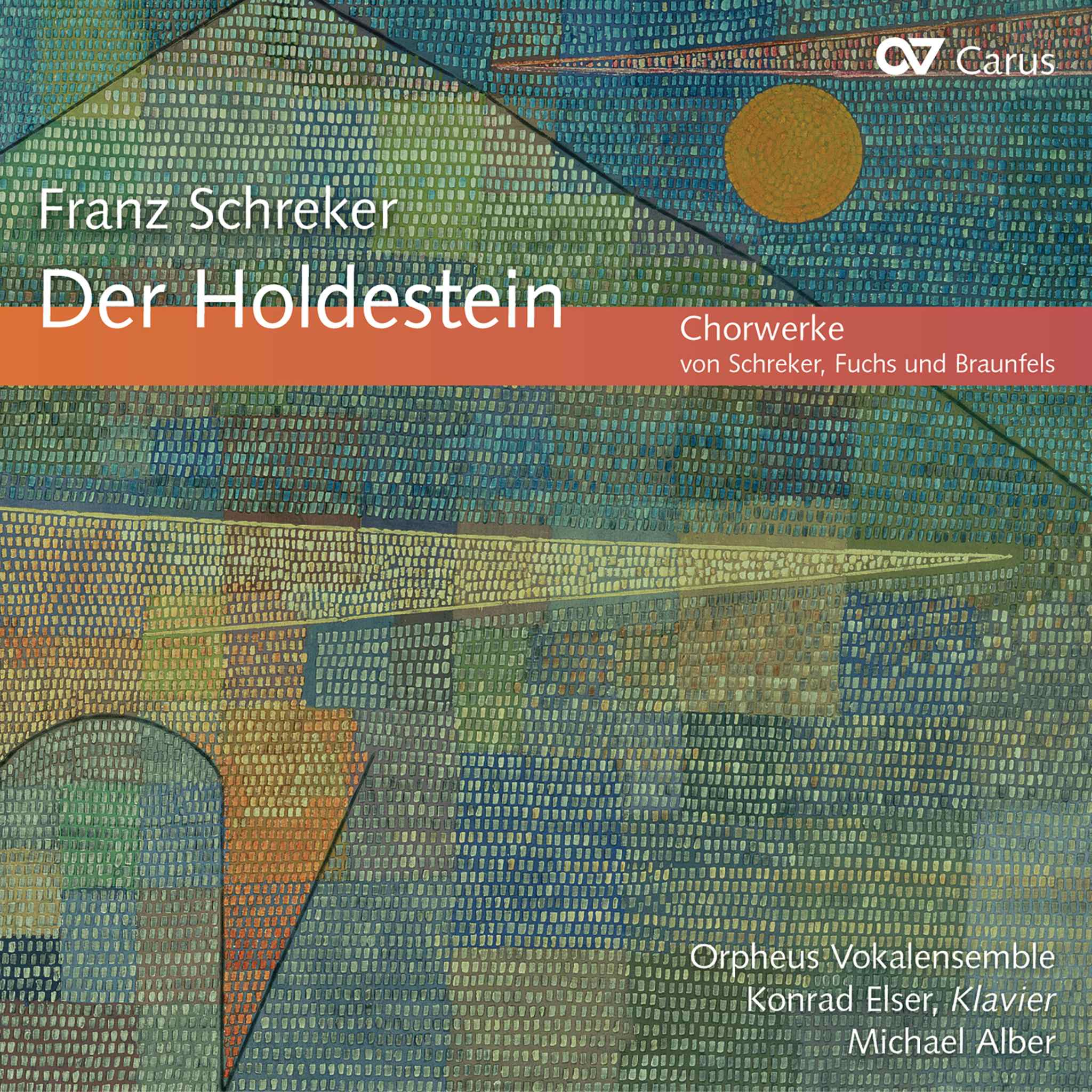アルバム
詳しく見るWalter Braunfels
ヴァルター・ブラウンフェルスは、1882年12月19日、フランクフルトで、法学者で文学者であったルートヴィヒ(ラザルス)・ブラウンフェルス(1810-1883)と、彼より32歳年下の二番目の妻ヘレーネ(旧姓シュポア)の末子として生まれた。アビトゥーア(大学入学資格試験)に合格し、1895年には入学していたホッホ音楽院での教育を終えた後、1901年にキールで国民経済学を学び始めるが、その後音楽の道に進むことを決意する。1902年にはウィーンに1年間滞在し、テオドール・レシェティツキーのもとでピアノの腕を磨き、カール・ナヴラティルから理論を学ぶ。1903年からはミュンヘンに移り、ルートヴィヒ・トゥイレに作曲を師事するが、そこで彼にとって最も影響力のある教師となる指揮者フェリックス・モットルに出会う。1903年からはモットルの助手としてミュンヘン国立劇場で働く。また、1903年からはピアニストとしても定期的に公の場で演奏活動を行った。
作曲家としての最初の大きな成功は、1909年にリューベックでヘルマン・アーベントロートの指揮により初演された交響的変奏曲 作品15と、シュトゥットガルトでマックス・フォン・シリングスの指揮により初演された最初のオペラ「プリンセス・ブランビラ」作品12(E.T.A.ホフマン原作)である。同年、彫刻家アドルフ・フォン・ヒルデブラントの末娘ベルタ・フォン・ヒルデブラントと結婚する。第一次世界大戦(1915年召集、フランスでの前線勤務、負傷)は、音楽的な側面だけでなく、彼の人生における転換点となった。前線での経験にトラウマを抱え、地獄を生き延びたことに感謝し、プロテスタントであったヴァルター・ブラウンフェルスはカトリックに改宗する。彼のオペラ「鳥たち」(アリストパネス原作)は、1920年にミュンヘン国立劇場でブルーノ・ワルターによって初演され、センセーショナルな成功を収め、彼の音楽的ブレイクスルーを意味した。
ブラウンフェルスの作品、例えば「エクトル・ベルリオーズの主題による幻想的出現」、「テ・デウム」、「緑のズボンのドン・ギル」、大ミサ曲、「ドン・ファン変奏曲」などは、ヴィルヘルム・フルトヴェングラー、オットー・クレンペラー、シリングスといった著名な指揮者によって演奏され、ほとんどすべてのドイツの舞台やコンサートホールの演目に取り上げられた。それらは国際的にも高く評価された。1923年にはベルリン芸術アカデミーの会員となり、1925年にはアーベントロートとともにケルン音楽大学の創設ディレクターに任命された。
1933年のナチス政権掌握により、いわゆる「半ユダヤ人」ブラウンフェルスの全作品が禁止され、彼はすべての公職から退くことを余儀なくされた。帝国音楽院は彼にいかなる音楽活動も明示的に禁じた。亡命する能力がないと判断した彼は、家族とともにスイス国境に近いボーデン湖畔に移り住んだ。1933年から1945年までの国内亡命期間中に、3つのオペラ「受胎告知」(ポール・クローデル原作)、「夢の人生」(グリルパルツァー原作)、「ジャンヌ・ダルク – 聖女ジャンヌの生涯からの情景」(裁判記録に基づく)、4つのカンタータ、3つの弦楽四重奏曲、1つの五重奏曲などが作曲された。
1945年、終戦後、コンラート・アデナウアーはヴァルター・ブラウンフェルスをケルン音楽大学のディレクターに再任した。復興期、そして1950年の引退後も、交響曲協奏曲 作品68、交響曲ブレヴィス 作品69、ヘブリディーズ舞曲 作品70、受難劇 作品72など、様々な作品が作曲された。彼は1954年3月19日にケルンで死去した。1945年以降、彼の作品は、当時優勢であったセリエル音楽に対して、なかなか評価を得ることができなかった。しかし、1990年代以降、後期ロマン派と古典的モダニズムの間に独自の位置を占める彼の作品は、再び頻繁に、そして国際的な成功を収めて上演されている。
スザンネ・ブルーゼ