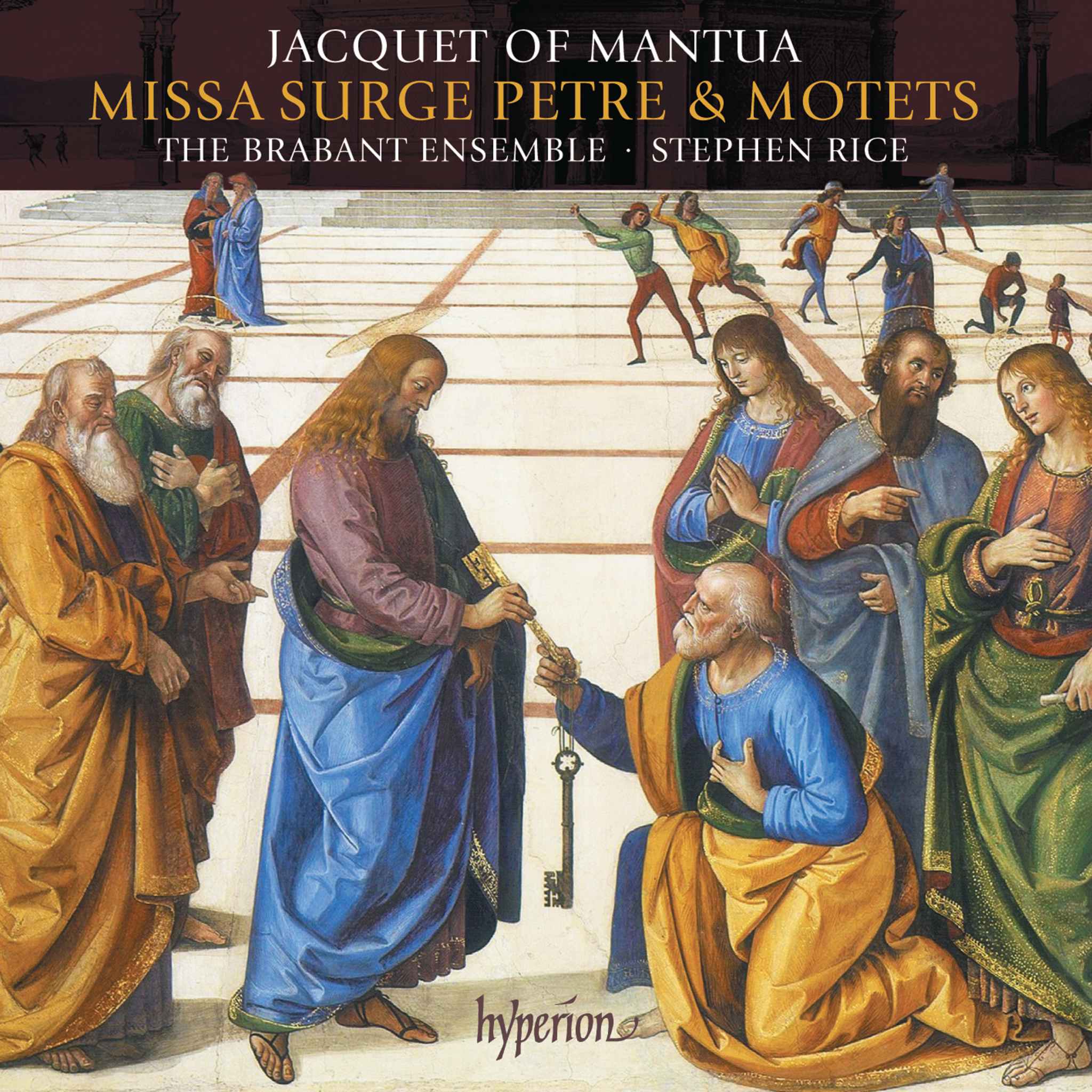ミサ・グレコルムの題名:なぜこの名がつけられたのか?明確な答えはありません。トーマス・ノブリットは、本録音への序文で、このミサの起源を解明しようと様々な学者が試みたが、成果はなかったと述べています。ミサのカントゥス・フィルムスは、特にそのリズム構造から、世俗的な起源を持つようです。「ギリシャ的」な要素は、復活祭にギリシャ語朗読を行うバチカンの伝統と関連している可能性があります。この仮説は、復活祭の連作「Victimae paschali laudes」の使用によって裏付けられています。「グレコルム」の旋律は、上声部で全体が表現される「アニュス・デイ」で最も明瞭に聴こえます。[1]エドガー・スパークスは、オブレヒトがミサ曲の様々な部分で、増大、転回、逆行といった洗練された変奏技法を用いていることを強調している。
オブレヒトがテノールから音楽素材を導き出した方法は、後の第二ウィーン楽派の技法との類似性を示している。アントン・ウェーベルンは、オブレヒトと同時代人であるハインリヒ・イザークの作品について学位論文を執筆した。この形式的な手法は、オブレヒトが対位法を組み込む枠組みを形成している。聴覚的印象は、和声的および構造的な変化から生まれ、オブレヒトの音楽的成熟度と均整感覚を前面に押し出している。
キリエとグロリアは、オブレヒトが様々な音楽構造においてカントゥス・フィルムスを巧みに用いていることを如実に示している。キリエでは、楽器編成の縮小が三重奏を示唆し、リズムの変化が複雑さの増大を示唆している。グロリアでは、カントゥス・フィルムスが様々な模倣形式で現れ、楽章は活気のある三拍子で締めくくられている。
クレドはレチタティーヴォで始まり、簡潔な物語へと展開し、グロリアのユニゾンとオクターブによる模倣を伴う活気に満ちた「復活して」へと繋がる。4つのセクションと最も長い緊張の弧を持つサンクトゥスは、ミサのクライマックスを象徴する。アニュス・デイは楽器編成を変えながらミサを締めくくり、オブレヒトの典型的な作曲特性を示している。
ミサ・グレコルムは1490年頃に作曲されたとされる[2]。オブレヒトは1505年に亡くなるまでヨーロッパで様々な役職に就いた[4]。彼の膨大な作品は、この作曲家の多才さと革新性を示しており、この録音によって現代の聴衆に彼の素晴らしさがより深く伝わってくる。
長めのモテット「オ・ベアテ・バシリ」と断片的な「マテル・パトリス」は、複雑なテクスチャのタペストリーを織り成し、テキストと音楽の見事な融合を示している。 「サルヴェ・レジーナ」と「アニュス・デイ」はオブレヒトの多様な作品のさらなる例であり、彼の幅広いレパートリーを豊かにしています。