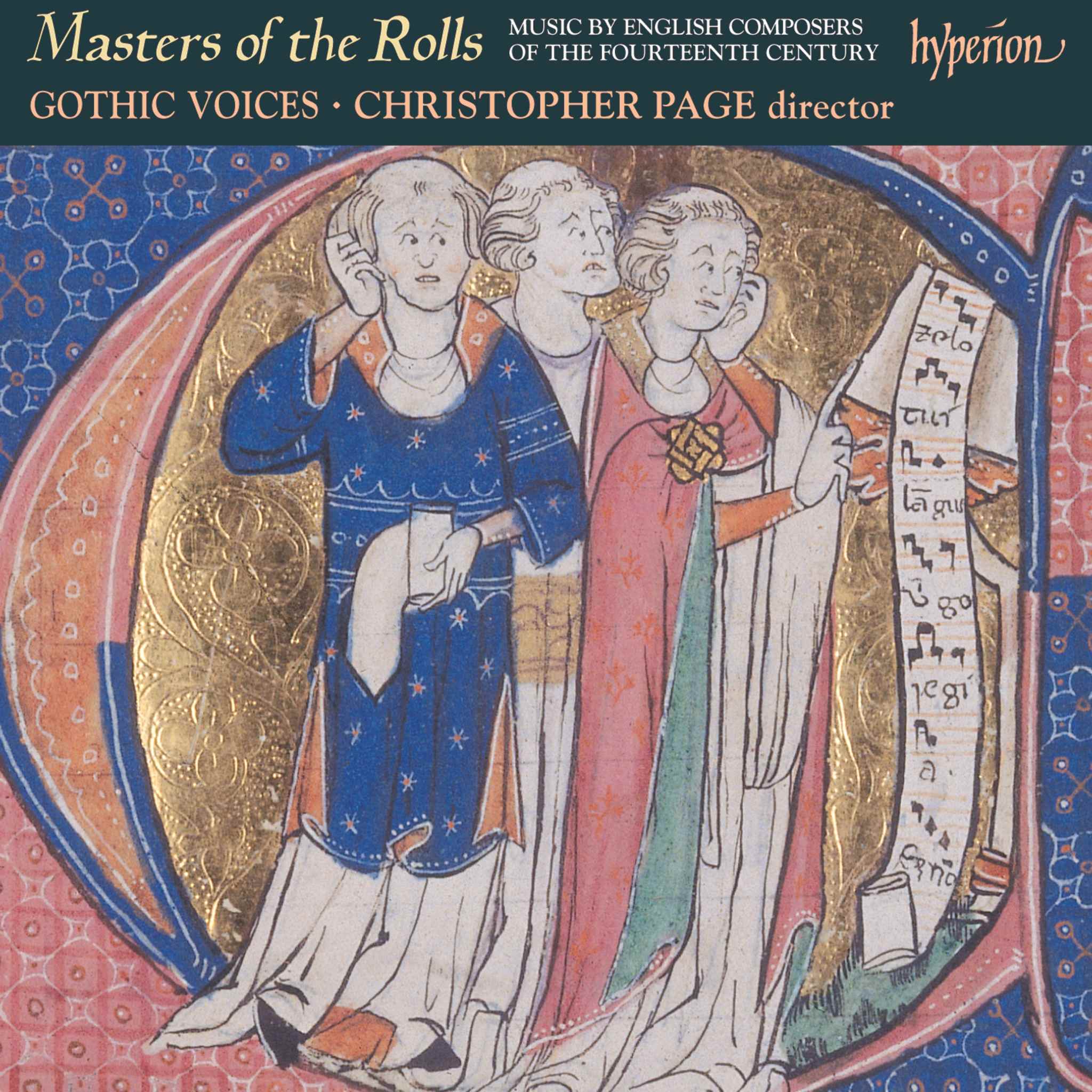ジョスカン・デプレの世代を代表する人物の一人、ピエール・ド・ラ・リューは、ハプスブルク=ブルゴーニュ宮廷の音楽監督を務め、輝かしいキャリアの中で数々の傑作を残しました。彼はその生涯を通じて、計29のミサ曲集、4つのミサ曲全曲、6つのマニフィカト、14のモテット、そして数多くの世俗曲を作曲し、同時代で最も多作な作曲家の一人となりました。彼の音楽的発展は、様々な活動の段階に反映されています。ブリュッセルとゲントの教会の記録には、歌手として初めて彼の名前が記されていますが、その後様々な仕事を経て、最終的にハプスブルク=ブルゴーニュ礼拝堂へと導かれ、そこで彼の芸術様式は進化を続けました。[4][5]
ラ・リューの作品にはすでに現代的な影響が見られていたため、アンサンブル「ゴシック・ヴォイシズ」は彼の音楽を演奏するという挑戦に挑みました。特に、低音域への強調と特徴的な音程の使用は、彼を中世の作曲家たちと区別する特徴であった。模倣やカノン構造といった作曲技法は彼の作品の特徴であり、これは歌手に多大な要求を課した「ミサ・デ・フェリア」によく表れている。ラ・リューは対位法と振付の繊細さに対する鋭い感覚を示した。
「ミサ・デ・フェリア」において、ラ・リューはローマ時代のカントゥス・プラヌスの旋律を取り入れ、それをカノン技法と巧みに融合させることで、ミサ曲に祝祭的な雰囲気を与えている。彼の作品の音響的構成は、強烈さと旋律の豊かさの洗練されたバランスに表れている。簡潔な形式と初期の作品への言及を特徴とする「ミサ・サンクタ・デイ・ジェニトリックス」もまた、作曲家の創造的多才さを示している。
さらに、ラ・リューのモテットのいくつかはリュート譜に編曲されており、これらの編曲は原曲を繊細かつ抑制的に再解釈している。クリストファー・ウィルソンの組譜は、ピエール・ド・ラ・リューの存命中に広まっていたフランドルおよび北西ヨーロッパのリュート演奏の典型的な伝統を反映しています。