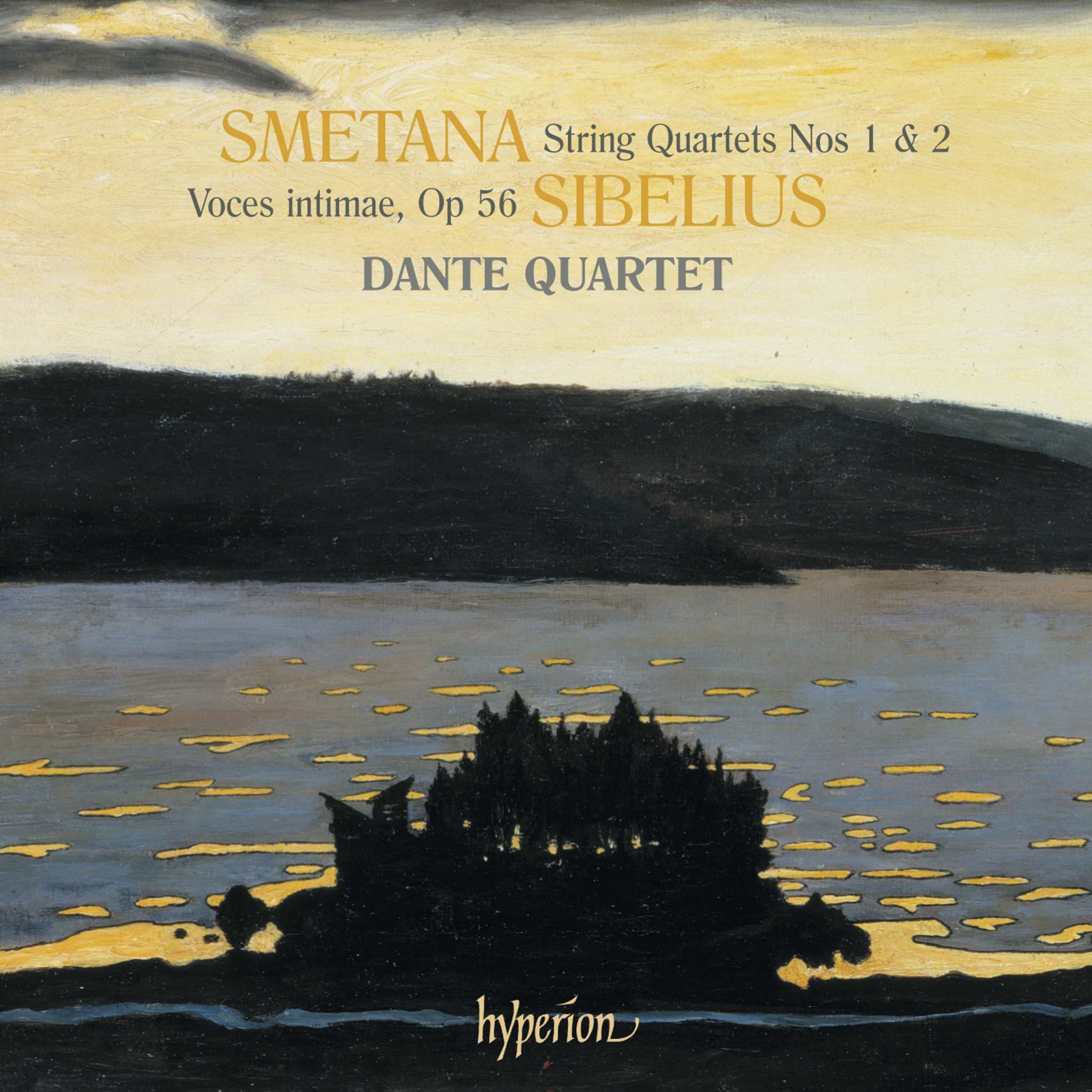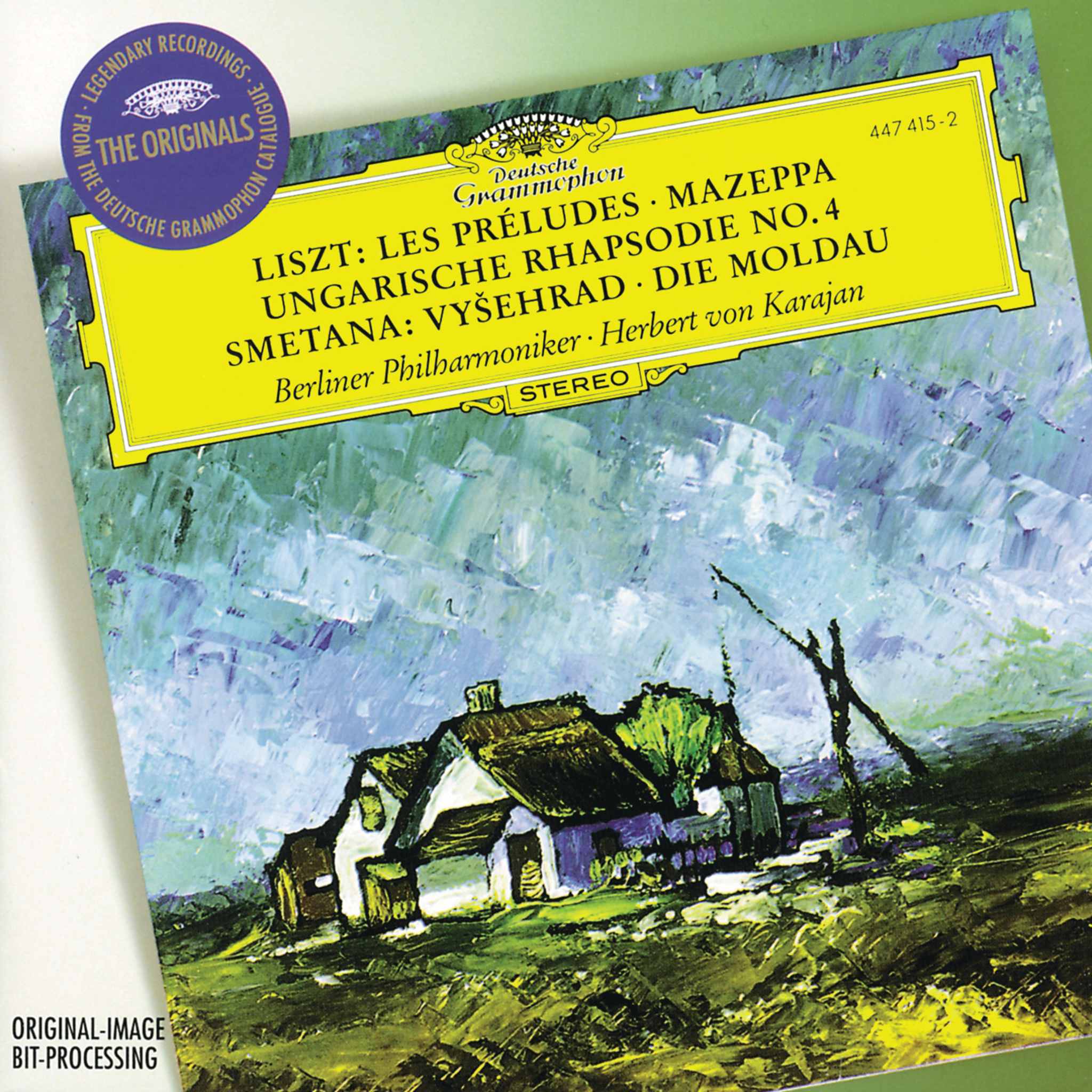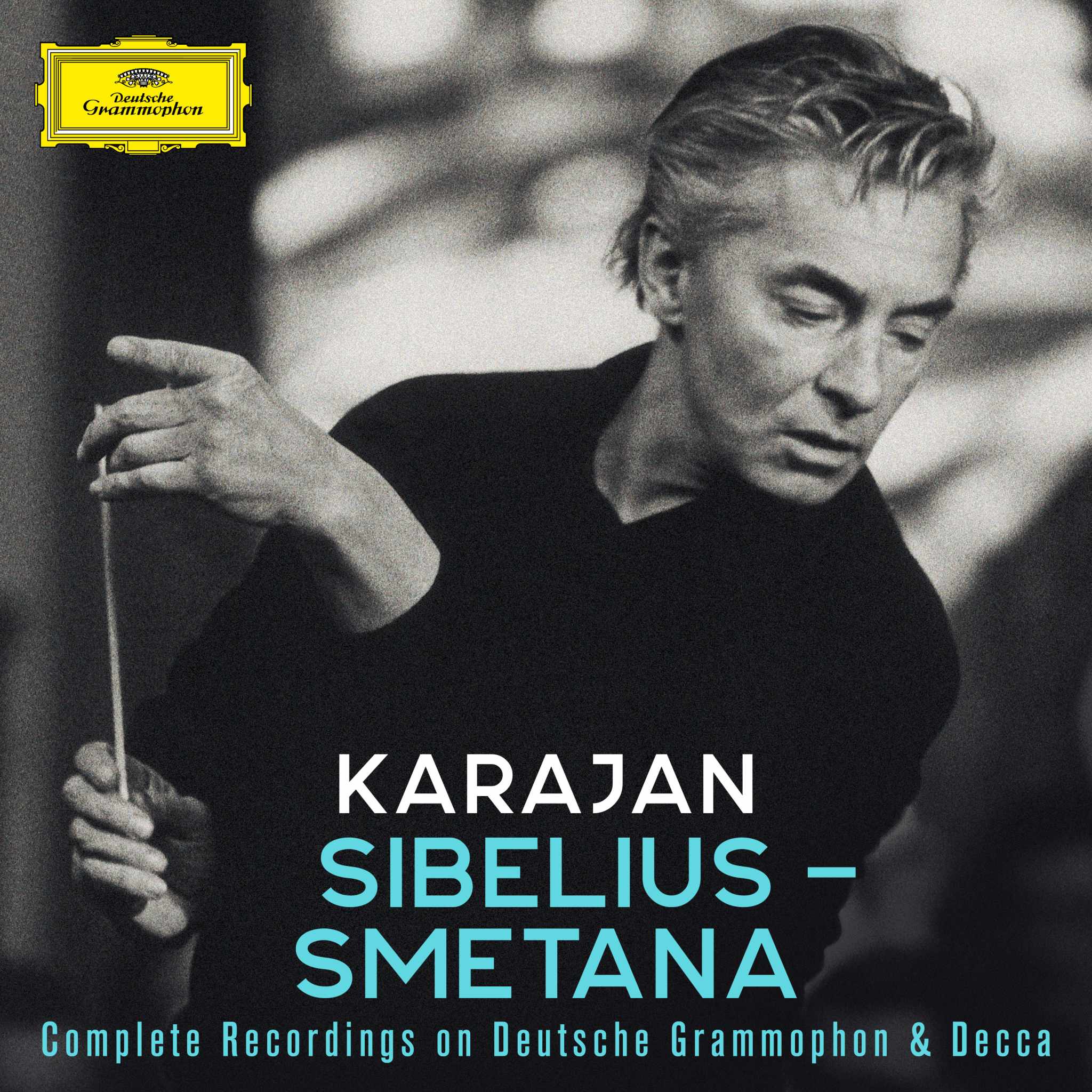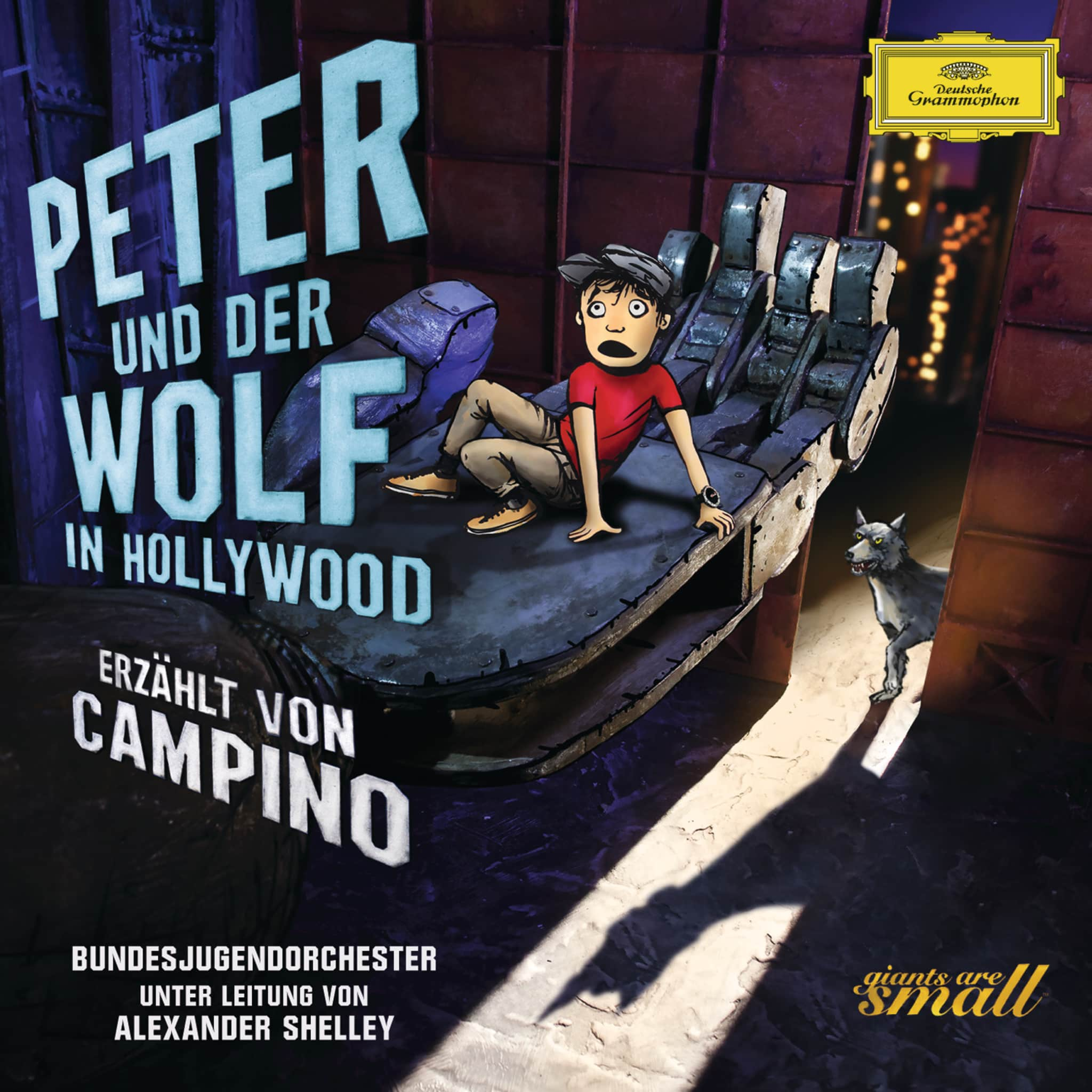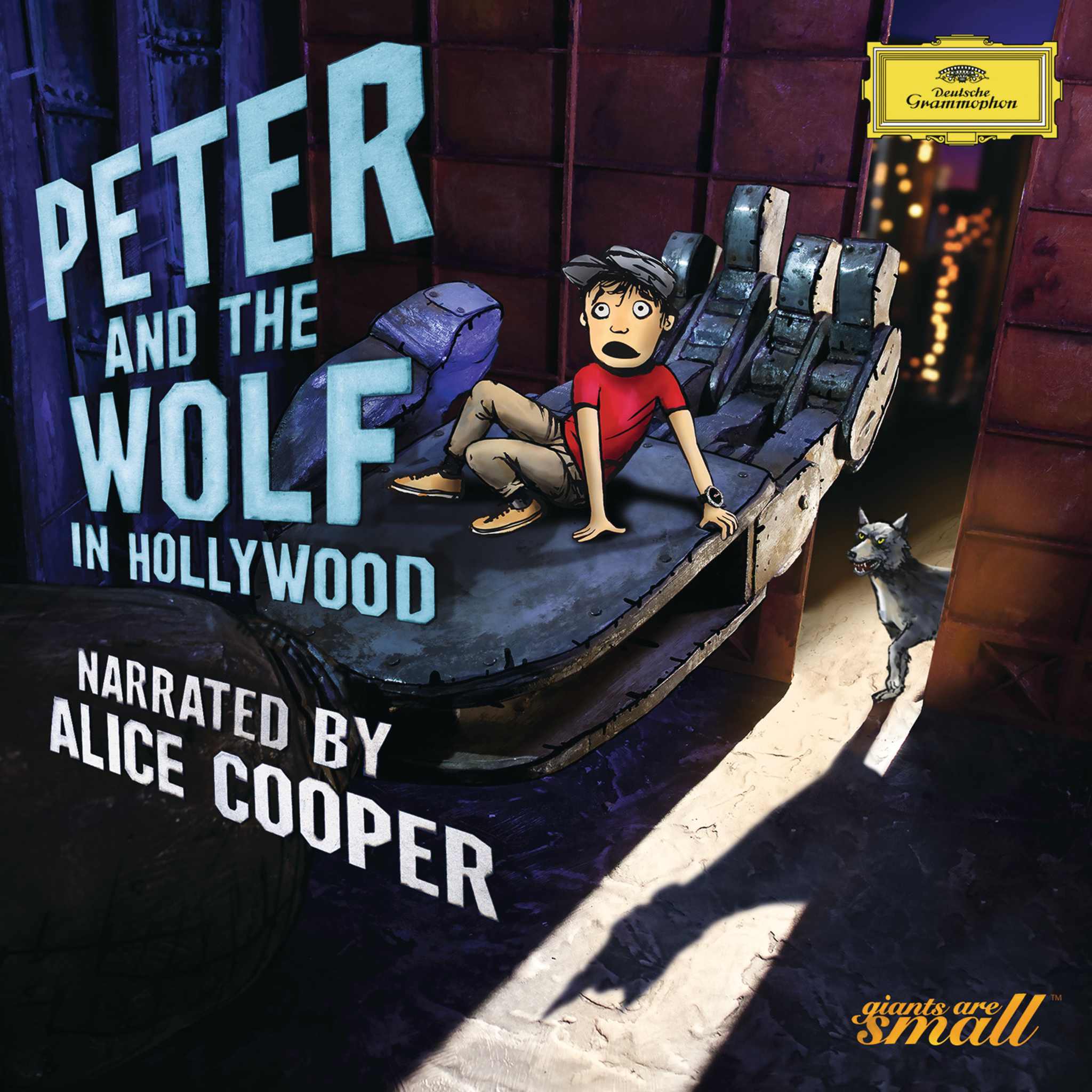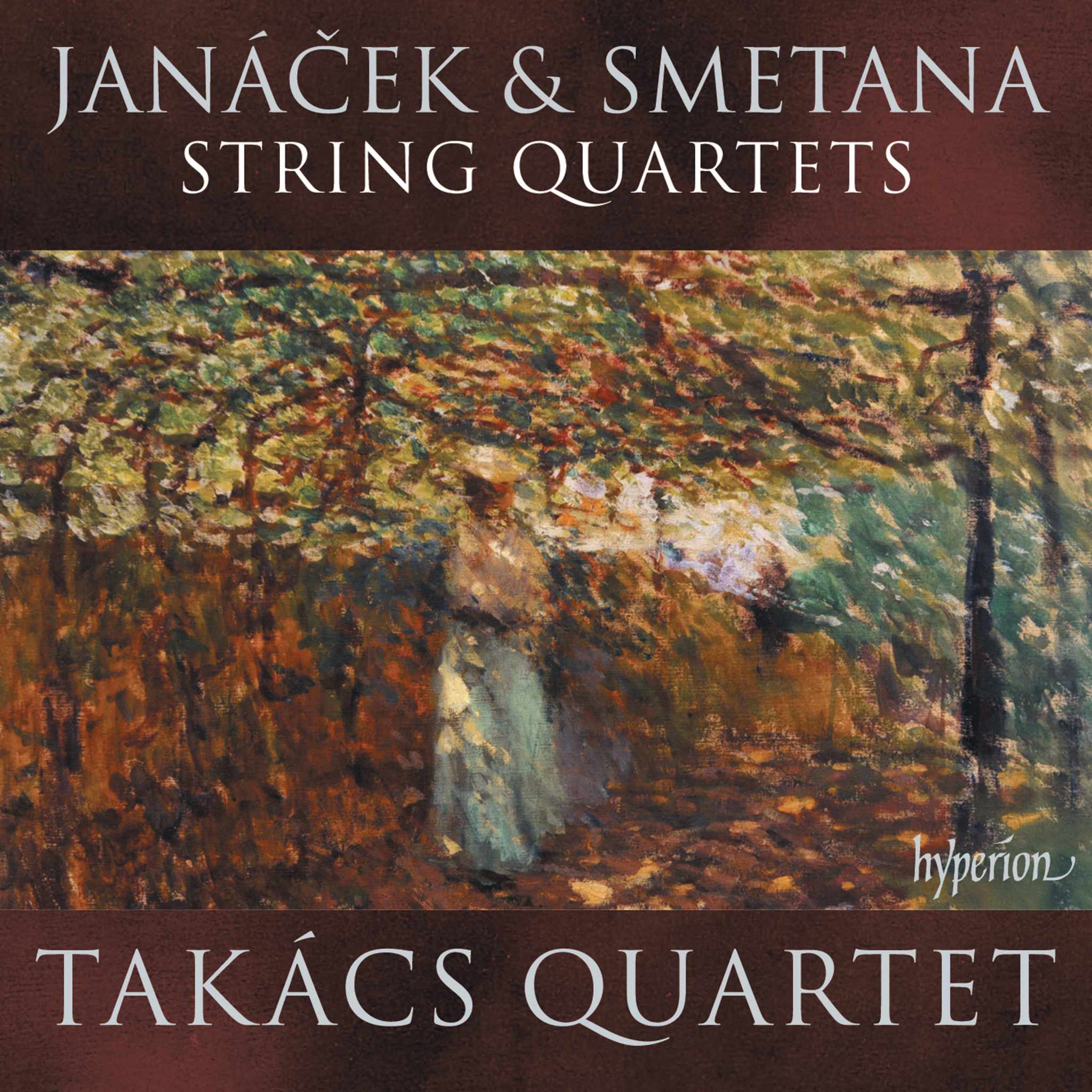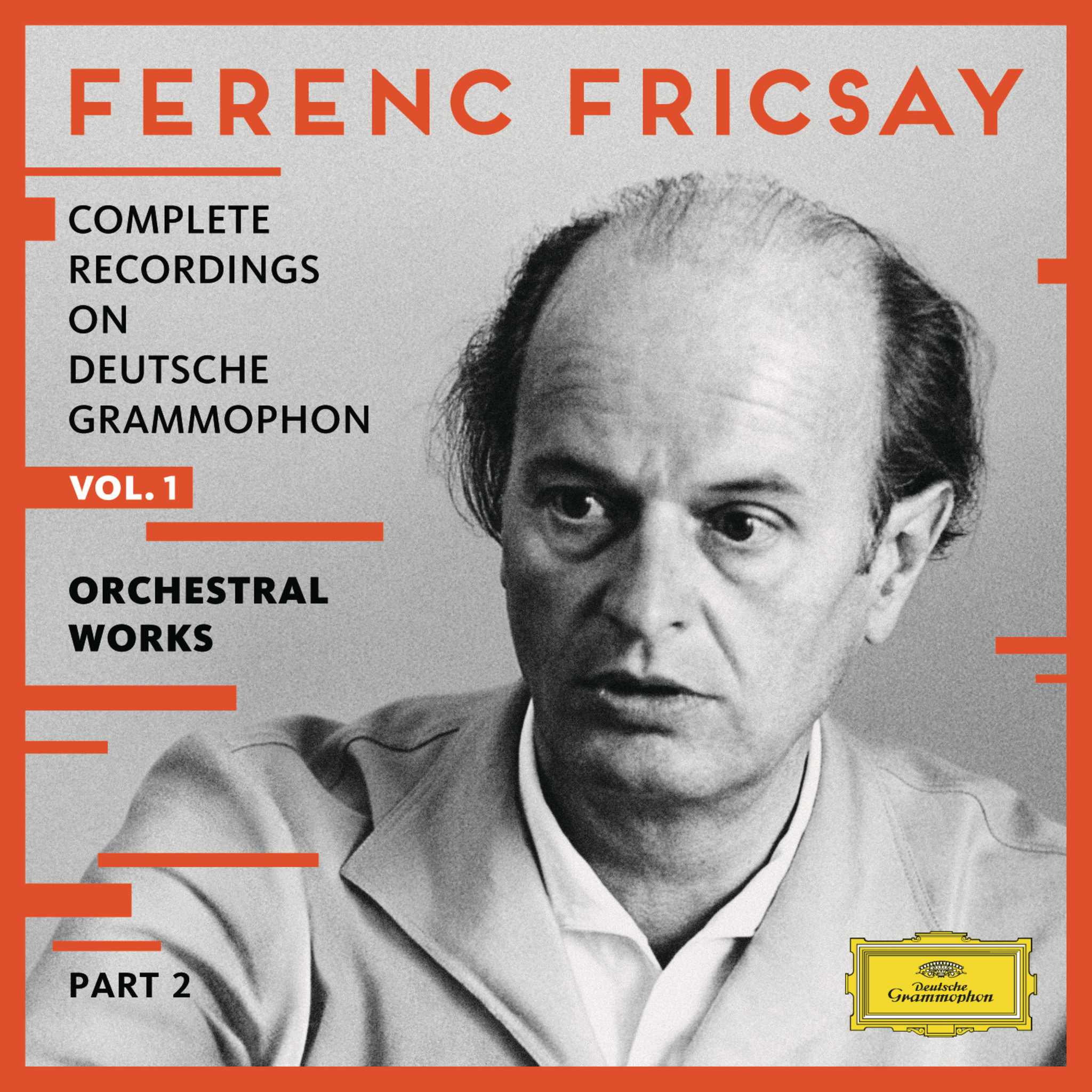コンサートとオペラ
アルバム
関連コンテンツ
詳しく見るベドルジーハ・スメタナ

ベドルジハ・スメタナ(* 1824年3月2日、ライトミシュル; † 1884年5月12日、プラハ)は、チェコ国民音楽様式の創始者とされています。プラハでピアノと作曲を学び、コンサートピアニストとしてのキャリアを築こうとしましたが、すぐに自身が設立したプラハの音楽学校で教鞭をとるようになりました。1856年にはスウェーデンからの招きでイェーテボリへ渡り、1861年まで指揮者、ピアニスト、講師として活動しました。その後、スメタナはプラハに戻り、チェコ音楽に深く傾倒しました。1866年にはチェコ国立劇場の指揮者に就任し、自身のオペラを上演するのに適した場を得ました。1874年からは聴覚が徐々に失われたため、活動的な音楽生活からは引退しましたが、亡くなるまで作曲家として活動を続けました。
初期の作品の一部は、当初フランツ・リストやリヒャルト・ワーグナーの様式的な影響を受けていましたが、ベドルジハ・スメタナはそこから独自の音楽的結論を導き出しました。彼は交響詩というジャンルにおいて、オーケストラ音楽と民謡的要素を巧みに結びつけ、プログラム音楽として表現する可能性を見出しました。その代表作である「わが祖国」(1874年~79年)は、チェコの故郷をはるかに超えて成功を収めました。また、「弦楽四重奏曲ホ短調『わが生涯より』」(1876年)など、いくつかの室内楽作品も人気を博しました。
ベドルジハ・スメタナの作品群の重要な構成要素は舞台作品です。「売られた花嫁」(1866年/70年)は、風俗画と控えめなリアリズム、舞踊歌のような旋律、そして演劇的な華やかさの融合により、ボヘミア・チェコの絵画的な魅力の象徴となり、国際的に人気を博しました。その他にも、「ブランデンブルクの人々」(1868年)、「ダリボル」(1868年)、「リブシェ」(1871年)、「二人のやもめ」(1874年)、「秘密」(1878年)、「悪魔の壁」(1882年)が制作され、さらに合計9曲の交響詩、「弦楽四重奏曲ニ短調」(1883年)、そして「ピアノ三重奏曲ト短調」(1855年)があります。ベドルジハ・スメタナがその後の音楽に与えた影響は大きく、特にアントニン・ドヴォルザークとレオシュ・ヤナーチェクは彼の音楽的功績を明確に参照しました。