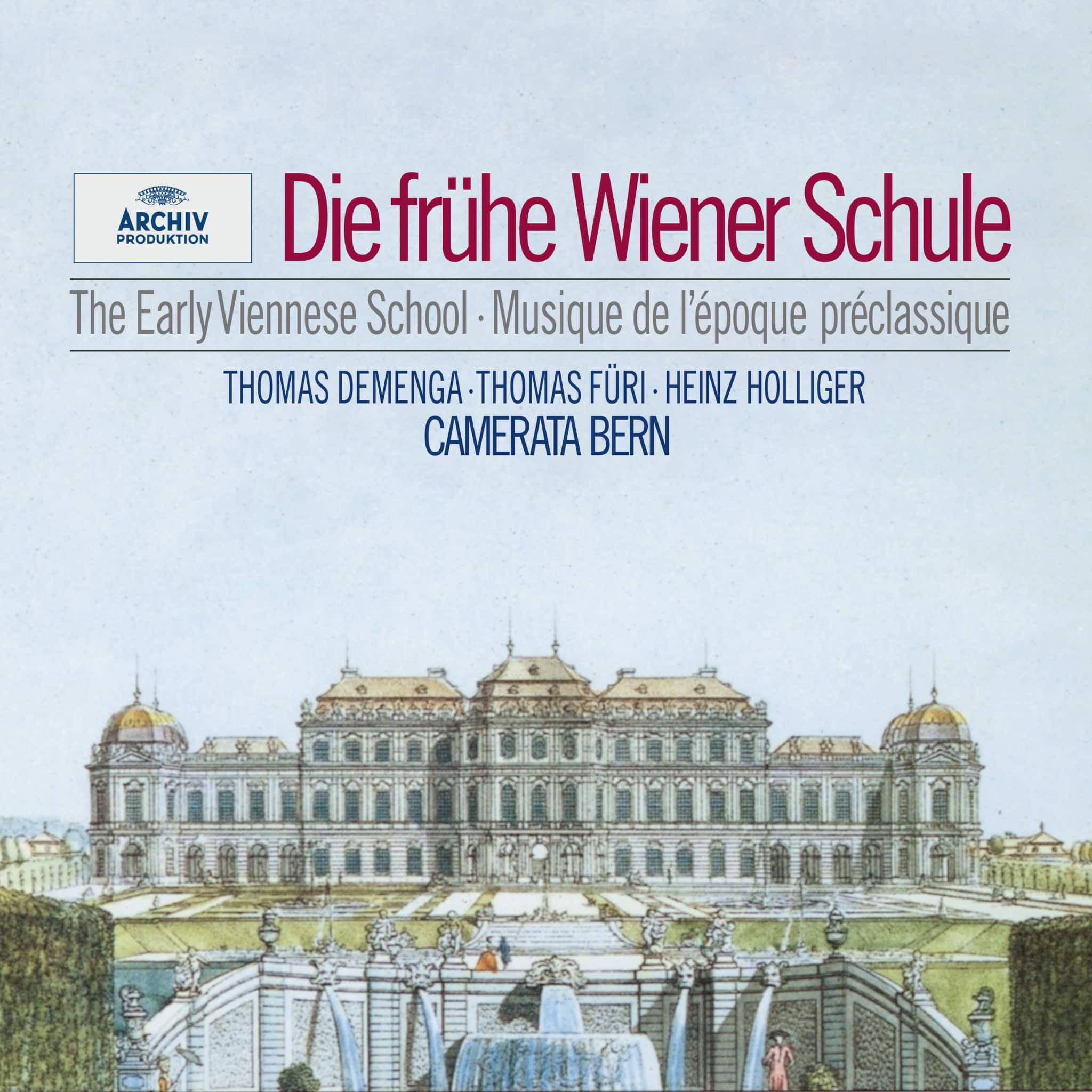Celebrating Antonio Salieri and the Vienna Boys Choir's 525th Anniversary
Delve into the captivating world of Antonio Salieri's notable compositions with STAGE+. As an internationally acclaimed composer, Salieri's works have been delighting audiences for centuries, and his significant contributions to the realm of classical music remain unparalleled.
The Vienna Boys Choir's 525th-Anniversary Concert
Join us in the Vienna Boys Choir for their 525th-Anniversary Concert, a fitting celebration featuring the aria for which Salieri wrote expressly for Francesco Benucci, the extraordinary performer who was also Mozart's first Figaro. This concert marks over five centuries of uninterrupted musical legacy, with the Vienna Boys Choir maintaining a position as one of the best-known boys' choirs in the world. The milestone was celebrated with a major concert at Vienna's prestigious Musikverein.
An unforgettable performance that rekindles the mutual respect and rivalry between Mozart and Salieri, this event promises to bring history to life. The anniversary events and related concerts typically feature a diverse program. For instance, a recent program included works by Purcell, Orff, Mozart and Schubert, alongside resonant modern selections from jazz great Oscar Peterson and ABBA. Mozart's Eine kleine Nachtmusik was highlighted, connecting to the choir’s Mozartian heritage and the symbolic 525th work in his catalog.
Exploring Salieri's Influence and the Era's Musical Connections
Explore songs by Schubert's friends and contemporaries, with a particular focus on Salieri's prodigious body of work. Presented by world-renowned pianist Graham Johnson, this program will offer a deeper exploration of the social and musical connections of that period, illuminating both popular and lesser-known works from this influential era.
Experience Authenticity with Antique Brasses
Experience the original brass music played on period instruments with the Antique Brasses performance. Embrace the magnificent sounds created by the London Gabrieli Brass Ensemble, conducted by Christopher Larkin, as they showcase Salieri's compositions in pure authenticity, dedicated to capturing the exact sound aesthetics of the era.
These performances not only elevate Salieri's distinguished works, but also bring us a step closer to understanding the musical genius that influenced so many future generations of musicians. This series at Musikverein, Vienna is a must-attend for classical music aficionados and those curious about the rich history of the genre.
Join us with esteemed guests Matthew Rose, Arcangelo, and Jonathan Cohen for a rewarding cultural expedition into the heart of classical music. Don't miss this chance to appreciate Salieri's enduring legacy firsthand.